|
危険の大きいデカい仕事にとりかかるには、すべてを万全に整えておきたい。
俺はしばらくの間、デルビンたちが仕入れてくる小さな仕事に精を出した。
カーリアの毒は俺にどんな後遺症も残さなかったが、完全に元のとおりに動けると自信を持てるまで、徹底的に自分の感覚を研ぎ澄ますことにしたんだ。
それに、雪帷の聖域での俺はすっかり油断して、思い上がってもいた。
俺にもそれを悔しいとか恥ずかしいと思う気持ちはあるし、なにより、今まではそれでしくじっても、自分が死んでなにもかも終わる、ただそれだけだった。仕事の成否は俺の問題じゃなく依頼人の問題だ。だがそのときは違った。たとえカーリアの依頼だとしても、俺自身がそれを完遂したいと思っていた。だから、それはもう俺の問題だったってことだ。
そんなのは初めてだったよ。つまり、他人事じゃなく自分事の仕事ってのは。
だが……いや、だから、かな。おそろしく充実してた。
こなしたのは小さな仕事ばかりだったが、俺はすべてに完璧を期した。なにをするにしても目的と意味を持たせた。
たとえばちょっとした泥棒の仕事は、今までだったら適当に忍び込んで、住民がいれば適当にその目をかわし、適当にこなしてた。見つからない自信があったし、見つかったところで金ですぐ解放されるってね。
だがそのときは、住民の不在を狙うと決めたら相手の行動パターンを徹底的に調べ、実際に不在の家に入り込むのでなければ失敗と見なしたし、在宅中を狙うなら本当に人がいるときに、侵入口から脱出経路、ブツのありそうな場所、すべて考えてから実行した。
それは別に目新しいことじゃない。シャドウスケールとして働いていた頃と同じだ。なにせあっちは、捕まったらその場で殺されて当然なんだからな。泥棒みたいに、檻に入れられてしばらく頭を冷やせと言われるとか、保釈金を積んで出してもらうなんてこともない。
まあつまり、自分を戒めて、小さな盗みの仕事にも全力で当たることにしたのさ。
ひと通りの街に出かけて、人様の家の中から貴金属を失敬したり、帳簿の数字をいじったり。そのすべてで決して誰も傷つけたり殺したりはしなかったし、誰かに見咎められることもなかった。だが不審に思われた瞬間はあった。俺はそれもミスと考えて、より完璧に実行するよう努力した。
そういったことはすべて、本命の大仕事のためのトレーニングでもあったが、もちろんその一つ一つで達成感てものもあった。
ただ、活躍しすぎると、やっかみも出てくる。
俺は、バイパーにはちょっと敬遠されはじめてた。こいつはスリの名人で、最初は自分から寄ってくるような愛想のいい奴だったんだけどな。メルセルの後釜を狙ってるって噂もあったし、そういう野心がある男にとっちゃ、腕のいい仲間ってのも良し悪しだよな。
けどそのあたり、別に俺が心配しなくても、デルビンとかブリニョルフがちゃんと見てたよ。叱ったり、宥めたり、ハッパかけたりしてさ。
ライバル意識を燃やして張り合ってきた奴っていえば、ガーサーだ。こいつは大柄なノルド……たぶんノルドで、俺よりも少し後に入った新参者だった。ヴェックスに勧誘されて入ったんだったかな。ともかくこいつはハナっからのし上がる気満々、それを隠そうともしなかった。
こいつは開けっぴろげで、どんな小細工もなしに正面から来る。俺はこれこれこういう仕事をしたぞ、おまえはどうだってね。それに、俺のほうがいい仕事をしたと分かれば悔しがりはしたが、それをぶつけるのは俺にじゃなく次の仕事にだった。
それにガーサーは失敗にいちいちへこまないタイプでな。不運だろうと自分のミスだろうと、それはそれ、次は次だ。まあ、そういう性格から分かるとおり大味で、しくじって保釈金を払わせてたこともけっこうあるが、それも込みでギルドじゃいいムードメーカーになった。
それまでくすぶってた連中も、俺やガーサーに刺激されたのか、仕事に出掛けることが多くなった。
それでもやっぱり思いがけないミスだのトラブルだのってものはあったが、そういうのに逐一腐らなくなったのは、ガーサーのおかげだっただろうな。
風向きはまだ悪かったが、少なくとも俺たちの士気はかなり上向きになっていた。
それになにより、この頃には少しずつ盗賊ギルド復活の噂ってのが流れはじめてた。俺たちがコツコツ重ねてきた小さな仕事、その手際が、チリツモでだんだん無視できなくなってきたんだ。
小さな被害かもしれないが、盗賊ギルドがまた活発に動き出したことは、世間の噂に登るようになっていた。
ギルドの復活が噂になれば、少しデカい仕事が舞い込んでくる。
デルビンたちはこれを"特殊任務"って呼んでいた。
俺はこれまでに一つ、その特殊任務をこなしていた。詳しい内容は省くが、ホワイトランの名家にコネを作ることに成功した、とだけは言っておこう。
そしてこのときに請け負ったのは、ウィンドヘルムでのものだった。
俺はこの仕事を試金石にすると決めた。
カーリアの仕事に取り掛かる前に、最後の仕上げとして、この一件で自分の回復度合いをはかるつもりでな。デルビンから聞いた分には、どうにも荒っぽいことが待っていそうだったからだ。
ウィンドヘルムはリフテンの北にあるデカい街だ。スカイリム全体では東の端で、スカイリムで最古の街だとも言われてる。
内乱のまっただ中にあっては、そこは片方の頭が首長を務める街だってことで、王宮近辺はぴりぴりしてたな。それに街の連中も両極端だった。威張りくさったノルド至上主義者と、それ以外さ。それ以外ってのは、ノルドでも差別しない奴等……そりなりの数ちゃんといたよ。そういう連中と、灰色地区にいるエルフたち、それから、海岸沿いの倉庫みたいな場所に押し込められたアルゴニアンのことだ。
灰色地区ってのは、街の東にあるスラムで、そこに住んでるエルフの大半がダンマーだからついた名前だ。レッドマウンテンの噴火から逃れてやってきて、辿り着いたのがウィンドヘルムだ。街に入れてもらえたんだからまだマシかもしれないが、もちろん街の連中にはそれを快く思わない奴も少なくない。
だがあいつらはまだ街の中だからマシだ。俺の同族たちは街の中に住むことも許されないんだからな。俺は同情心や義憤ってものはほぼ持ちあわせてないが、それでもいい気分はしなかった。
それに、年がら年中いつ行っても雪が降ってることがあって、はっきり言って、俺にとっちゃスカイリムで一番気に入らない街だった。
だがもちろん、そこにいる全員、そこにあるなにもかもが嫌いだったわけじゃない。
俺が会った……そうだな、この人は世間的にはちゃんとした真っ当な稼ぎ人だし、身分と名前は秘密にしよう。アンタが聞いた話をどうするのかは知らないが、聞いて満足それっきりで、誰にも言うつもりないってわけじゃないんだろ? ……まあまあ、それはいいよ。聞く気はないから話さなくていい。気になってたら、話をする前に確認したさ。
まあとにかく、その男のことはここではTCって呼んでおこう。ウィンドヘルムでなかなか成功してる、そうだな、農園主だ。
この男のことは、ウィンドヘルムに立ち寄ったときとか、そこで仕事をしたときに何度か見かけていたし、実は話したこともあった。近郊に立派な農園を持った成功者だが、自分で畑仕事をするような男で、気取りもなく、家族や雇人にも評判のいい男だった。
だから俺は、依頼人の名前を聞いたときには意外な気がしたんだ。そんな真っ当な男が、盗賊ギルドなんかに? ってね。
だが実際にウィンドヘルムに出かけてその男を探し、ギルドからの遣いだと名乗ると、TCは驚いた顔をしたが、余計なことは言わず、農園まで来てくれと俺を誘った。
案内された農園は、それほど大きくはなかったが手入れが行き届いていて、納屋も小奇麗だった。その藁山の一つに腰掛けて、TCは仕事の話をはじめた。
TCの依頼は、盗賊に持ち去られた娘のロケットを取り返してほしいってものだった。
話は少し遡るんだが、TCはひとつきほど前に娘を殺されていた。その娘ってのは、貴金属をじゃらじゃらつけて歩くような、まあ親父と違って頭の良くない見栄っ張りで、ある日街の中で殺され、身につけていたものを奪われたんだ。言ってみれば自業自得だが、父親としては当然仇を討ちたい。それに、持ち去られた装飾品の中に、家宝でもある「銀のロケット」があった。
仇を討ち、ロケットを取り戻してほしい。それがTCの頼みだった。
聞いて、俺がまず思ったのは、それをどうして盗賊ギルドに頼むのかってことだ。殺人事件に窃盗なら、衛兵に頼めばいい。なにせノルドだ。ノルドのはずだ。あの街の中に立派な邸宅を持ってるくらいなんだからな。衛兵だって喜んで働いてくれるだろう。
俺は疑問に思ったことをできるだけ尋ねることにした。適当に二つ返事で引き受けて、やってやれないことはないだろうが、それは"仕事"に対していい加減な、油断した態度だ。そういう油断は一度で十分、もう懲り懲りさ。
TCの話じゃ、衛兵はウルフリックの私兵みたいなもので、今は内乱に対する備えでまともに取り合ってくれなかったってことだった。それに、無理に嘆願して引き受けてもらえたとしても、まともに捜査してくれるとは思えなかったそうだ。ロケットにしても、「銀? つまりただの銀製か?」。これはTCが言われた言葉そのままだ。つまり、真剣に探してくれる気がしなかった。
だからTCは盗賊ギルドを頼った。
それに、TCには以前、ギルドとつながりがあった。あんなに落ち目になる前には、この街での協力者、庇護者だったんだ。衛兵の一部を買収したり、あるいは保釈金を積んだりってね。
TCって男は、真っ当な農園主に見えた。実際、普通の人だった。まあ、盗賊に協力するって時点で完全な善人じゃないかもしれない。だが、決して悪人じゃない。あえて言うなら、彼は至極真っ当だからこそ、盗賊ギルドを選んだって言ってもいい。
っていうのは、そうだな……。俺は話を聞いて、一つ不思議に思った。
「アンタはこれを、盗賊ギルドの仕業だとは思わないのか?」
ってことさ。娘が殺されて、金目のものが盗まれた。だったら、盗賊ギルドの奴が疑われたって無理はない。
けど、俺のその疑問にTCははっきりこう言った。
「きみたちは決して、盗むために殺しはしない。そうしなければ盗めないとしたら、それを恥だと思うはずだし、そんなやり方に不愉快を感じるはずだ」
ってね。
それを聞いて、俺は妙に納得した。なんとなくもやもやしてたものが晴れたような感じだった。
ああ、これが恩恵だったのか、って。
"殺すな"って掟のことさ。殺し屋だった俺が、最初の頃、二、三人殺して吊るせばいいのに何故、なんて思ってたことへの答えだ。
そう。もしギルドが簡単に人を殺していたら? 言うまでもないよな。TCみたいな普通人は絶対に関わろうとしなかっただろう。それに、この事件もギルドの仕業かもしれないと疑われたはずだ。
だがギルドは、どんなに落ちぶれても殺しはしなかった。メルセルの野郎はどうか知らないが、少なくともブリニョルフたちの目が届く範囲では、あいつもそんなことは良しとしなかったはずだ。
だからこそ、普通に暮らしてる人でも少しなら関わってもいいと思うし、金と引き換えに大目に見てやってもいいと思う権力者だって増える。殺しの絡んだ厄介な出来事は、ギルドのすることじゃないとは信じてももらえる。
今TCがギルドを疑わず、取引を持ちかけてきたのも、俺が、いや、俺たちが掟を守ってこれまで活動してきたからこそだった。
それに、ギルドってのはその業種の特権階級の集まりみたいなもんだから、よそ者にデカい顔されるのは気に食わない。
盗賊ギルドの場合も同じだ。ギルドに参加していない盗賊が縄張り内で好き勝手やりはじめたら、ここが誰の持ち場なのかを教えてやるのが当然になる。
ってことは? 比較的真っ当な連中に任せておけば、それよりタチの悪い連中を排除してくれるってことだ。
TCが盗賊ギルドに手を貸したてきたし、そしてまた関わりを持とうとするのには、そういう理由もあっただろう。
ともかく、TCにはこの件についてまだ言っていないことがあるようだったが、それはどうやら、言っても構わないが言いにくいことのようだった。後は自分で調べて知ってくれ、っていうような気配があった。
彼は最後に、ニラナイっていうアルトマーの露天商がなにかを知ってるはずだと教えてくれた。もちろんTC自身もあたってみたが、なにも話してくれなかったらしい。
俺は聞かされた名前を少し意外に思いながら、TCの農園を出た。
時刻はもう夕方すぎで、そろそろあたりが暗くなる頃だった。このまま市場へ行けば、少し待つだけで帰宅途中のニラナイを捕まえられると思った。
ニラナイってアルトマーのことは俺もよく知っていた。市場に雑貨の露店を出してる女で、俺みたいなアルゴニアンにもいつも愛想がいいし、武器防具から本、薬、日用品まで、なんでも買い取ってくれるからすごく便利だったんだ。
それに彼女は、エルフ同士はもちろん、差別主義者以外のノルドとも仲が良くて、時には街の人の相談に乗ってるところを見たりもした。
だから、そんな彼女が強盗殺人に関係してるなんて、さすがの俺でもちょっと考えられなかった。
だがとにかく話が聞けないか試してみよう。そう思って少しだけ市場の傍で待ち、彼女が帰り支度を始めた頃合いに、世間話みたいに声をかけた。
 種族が違うとなかなか顔が覚えられないものだが、彼女はそろそろ俺を見分けられるようになっていていた。 種族が違うとなかなか顔が覚えられないものだが、彼女はそろそろ俺を見分けられるようになっていていた。
店じまいの時間にも関わらず、お得意さんならって感じで、なにか売りたいものでもあるのかって聞かれたから、俺は近くに誰もいないことを確かめて、TCの娘について聞きたいことがあると伝えた。
途端に彼女の顔が強張って、明らかに俺を拒絶するうな気配になった。
ニラナイは、そんな子のことなんて知らないし、疑われるなんて名誉毀損で訴えてやるとか息巻いていたが、真実味はなかった。不安や恐怖を覚えたとき、かえって強く噛み付こうとする。それそのものだよ。
だから俺は、ヘタな演技の必要なんてない、俺はアンタが人殺しそのものに関わってるとは思わない、ただ解決を頼まれてるだけなんだと話した。殺された娘の父親が、仇を討ちたいと願ってる。俺がそう言うと、ニラナイはだいぶ考えて、話したら自分の身も危ない、俺に守ることができるのかって訴えてきた。
彼女は犯人に脅されていた。だから、なにかを知っていても、自分の身の安全のために話すことができなかったんだ。
俺はギルドの者だってことを話し、もし身を守る必要があるなら、仕事の関係者として必ずギルドが助けてくれると約束した。
そうしたら彼女、えらく驚いた目で俺を見てね。ギルドのメンバーだとは思わなかったって言ったよ。ま、俺の偽装は大成功してたってことだな。あと、その口ぶりで、彼女自身ギルドに無関係でもないとも分かった。「ギルド」って言い方が、なんとなく身内っぽかったからな。
なんにせよ、それで安心したのか、そのまま売買の駆け引きでもしてるみたいに、小さな露店の屋根の下で事情を教えてくれた。
ニラナイの話によると、TCの娘を殺したのは"ブッチャー"って殺人鬼だし、それはTCも知ってるはずだってことだった。
ブッチャーってのはその頃ウィンドヘルムに出没してた猟奇殺人者で、若い娘を殺しては体を切り裂き、時には一部を持ち去っていく変態だ。俺も野次馬に惹かれてつい覗いたことがあるが、あれは悲惨な死体だった。TCの娘も同じようにされたのかと思うと、さすがにひどいと思ったほどだ。
人殺しがなにを言うって思われそうだが、俺たちは仕事の必要上、瞬時に殺して即座に立ち去るから、傷は致命傷が一つ、声も立てない内に即死だ。少なくとも無駄な苦痛や、過剰な暴力には縁がない。……まあ少なくとも俺は、そういう仕事をしてきた。
それに、その頃の俺には顔見知りとか、そういう人たちに対する……同情? なんかそういうのも生まれてきてたから、あの人の好さそうな農園主の娘がこんな有り様で殺されたのは可哀想だと思ったし、そんな死体を見たおっさんがひどいショックを受けただろうってことも想像できた。
じゃあ、俺が探す娘の仇ってのは、ブッチャーなのか? なにげなくニラナイにそう言うと、彼女は「そっちは後回しでいいと思う」と言った。ブッチャー探しのほうは、腕の立ちそうなカジートと、頭の良さそうなアルトマーが組んで、既にあれこれ調べているらしい。だからそっちは、ブッチャーの正体が分かるまでは放っておいてもいいだろうし、もしかするとその二人が始末もつけてくれるかもしれないってことだった。
だったら俺はそれに便乗しよう。
とすると、当面取り組むべきはロケットのほうだ。
このあたりで、露店の前での立ち話も不自然になってきたから、俺たちは宿屋、キャンドルハース・ホールに移動することにした。
あの街じゃノルドとそれ以外って区分だから、アルトマーの女とアルゴニアンの男がちょっと意気投合して、一緒に少し飲もうってことになったってそれほど変には思われない。ホールの二階にはいくつかのテーブルがあって、一つはたいてい物書きが占拠してるが、逆の一つは周囲に人もなく丁度いい具合だった。
ニラナイはなかなか優秀な二重生活者だった。こういうとき、慣れてない奴はつい、聞かれもしないのに「つい気が合って」とか言い訳をするもんだが、彼女はそういうことは何一つ言わなかった。むしろ、なにかの儲け話でも持ちかけられて、早く続きが聞きたいって様子だった。下手な演技なんて言ったが、よっぽど追い詰められないかぎりには、彼女の演技は十分以上に上手だった。
それで俺たちは、ごく自然に人を遠ざけて、話の続きをはじめた。
ニラナイによると、TCの娘を殺したのはブッチャーだが、ブッチャーは体を切り刻みその一部を持ち去ることはしても、金品には一切手をつけたことがないという。
むしろ窃盗は、遺体が死者の間に移された後に起こった。
葬儀の手順は種族によって違うし、同じノルドでも家のならわしなんかで少しずつ異なるが、TCの家はそう特別なことはなく、アーケイの司祭に遺骸を任せ、その翌日か翌々日には葬儀、埋葬という流れのはずだった。
ところがその夜、死者の間に"ある盗賊団"が入り込んだ。
「あいつらは……最低よ」
そう言ったニラナイの声は震えていた。怒りと、嫌悪だったと思うね。
ある盗賊団ってのは、「サマーセット・シャドウズ」と名乗るアルトマーの集団のことだとニラナイは教えてくれた。ニラナイにとっては同族の面汚しでもある。しかもそいつらが、ニラナイを脅して言いなりにしていた。
でも彼女はまず俺の仕事のほうだと、話を続けた。
サマーセット・シャドウズのリーダー、リンウェって男は、「死体から盗むのが好きな変態」だと彼女は言った。
俺はその言いように少し引っかかりを覚えた。墓泥棒は別に珍しくない。抵抗もされないし、高額な金品が副葬品として埋められていることもある。死者を冒涜すると感じれば不謹慎かもしれないが、変態って言い方は妙だ。
だが、だから、もしかしてと思い当たることがあった。
さすがに俺でも、シャドウスケールの連中みたいな感覚の狂った奴等相手ならともかく、普通の相手にはちょっと口に出せないような思いつきだ。
だがアンタには、話したほうがいいんだろうな。あくまでも物語として。
俺が思いつき、ニラナイに確認はしなかったし、TCには尚更やめておいたこと。
それは、リンウェが死者から盗むのは金品だけじゃなく、貞操や貞節、尊厳もってことじゃないか、ってことだ。
つまり、奴はおそらく、死姦の趣味があった。……と、俺は、思ってる。確認は取ってないがな。
まあたぶん、TCが語らなかったことも、これだろうと思う。ブッチャーがどんな殺人鬼かは、ウィンドヘルムに暮らしていれば知らなかったはずがない。にも関わらず彼は、死体から盗んだ別の犯人がいるはずだってことを言わなかった。それを言えば、このあたりのことにも話す……どころか、記憶が蘇るからだろう。だから、ブッチャーに切り刻まれて盗まれた、ただそういう悲惨さにしておきたかったのかもしれない。
ニラナイとは、かわした視線でなんとなく通じたと思う。
「そんな奴よ」
とニラナイが言った。
彼女は"そんな奴"脅されてるんだ。自分たちの盗品の窓口になれ、さもないと殺すって。彼女が必要以上に怯えるのも無理はないよな。殺された"後"までありかねないんだからな。
彼女は俺に、あいつらをなんとかしてくれたら、前のようにギルドと仕事をすると約束した。むしろ、だから守ってほしいとすがるようで、必死だった。
俺はさすがに、リンウェって野郎には気分が悪くなった。その気分の悪さは、アンタやニラナイ、TCみたいな、比較的真っ当な人の感じるものとは違うだろう。でもそれでも、こいつは殺したほうがいいし、殺して終いにしたほうがいいと思った。「へえ、そう。そんな奴もいるよな」じゃなくてな。
俺はニラナイから、奴等が隠れ家にしている場所について聞いた。ウィンドヘルムの西、そう遠くない場所にある……えーっと、たしか……ああ、そう、アターリング・ヒルズ? だったっけ? なんかそういう名前の洞窟だ。
街のすぐ傍を流れる川沿いに西進して行けば見つかるだろうってことだった。
時間はかけられない。ニラナイは嘘が上手なほうだが、命がかかっていても平然と振る舞えるほど豪胆じゃない。奴等に接触したら、俺に密告したことがバレるかもしれない。
だから俺は、ニラナイから話を聞き、場所と、そこまでどれくらいかかるのかを確かめると、すぐ向かうことにした。
ウィンドヘルムまで行ってTCに会う、ニラナイと話す、そこまでずっと休みなしで、もう半日以上が経過してたから、当然少し疲れてはいた。だが、仕事が常にベストコンディションでできるとは限らない。この程度の負荷は、不測の事態としてありうることだ。一晩休んでコンディションを整えて、なんてやるよりも、むしろこの状態で最高の結果が出せてこそ、自分の望むものだと思った。
それにたぶん……少しだけだが、リンウェって奴を一刻もはやく始末したいっていう……許せないとまでは言わないが、なにかそういう気分もあったと思うよ。らしくないけどな。
洞窟はすぐに見つかった。街道から少し引っ込んだところにあったから、なにも知らなければ通り過ぎたかもしれない。俺はニラナイからだいたいの距離を聞いていたし、そのつもりで近づけば人の話し声も聞こえてきた。よくあることさ。入り口の見張りを頼まれた奴等が、退屈だからって無駄話に興ずるなんてのはな。三流の証さ。少なくともブリニョルフやヴェックスがそこにいたら、無駄口叩くなって怒るだろうよ。
俺のプランはシンプルだ。誰にも姿を見られずに、全員排除し、目的のものを持ち帰る。リンウェをあっさり殺すのは足りない気がしたが、それは考えなおした。そんなことを考えれば、相手に反撃の隙を与えることにもなる。
外にいた見張りは2人。木立の陰から近づいて、一方が背を向けた隙に1人。振り返って死体に気づいて驚いている隙にもう1人。……このあたりは、あんまり具体的に語るのはよしとこうか。
 中に入ると、洞窟はすぐに、人工の建物につながっていた。奥に牢屋があったところを見ると、元は小さな砦だったんだろうな。だがそこにいた連中は、全部で15人に満たなかったのは確かだ。 中に入ると、洞窟はすぐに、人工の建物につながっていた。奥に牢屋があったところを見ると、元は小さな砦だったんだろうな。だがそこにいた連中は、全部で15人に満たなかったのは確かだ。
砦自体も小さなものだったが、少人数ってのは駄目だな。誰かが殺されても、それに気付かないままになる。見張りや見回りはせめて二人一組にして、片方がやられたらもう一方が大声を出す暇くらいないと。
それに罠もろくになかった。いくらかは申し訳程度に設置されていたが、あんなのは駄目だ。とりあえず置いてみましたって程度でさ。いいトラップってのは、ついうっかり踏み込むところに置かれている。一つの罠を抜けて油断した場所や、長い探索で集中力が切れかけた頃。そういうところにあれば、単純なベアトラップにだって引っかかるし、宝箱には無警戒に手を伸ばす。"立て続けに置かれていたかと思ったら、抜けた先に一拍置いてまたある"。そういう、巧みに配置されてたカーリアの罠でさえ、それそのものは俺をさして煩わせなかったんだから、あいつらの仕掛けたものなんて尚更だった。
少なくとも、本気になってる俺を騙せるようなものは一つもなかった。
 もちろん、造作もなかった。拍子抜けだったよ。この程度で盗賊団気取ってたのかってね。 もちろん、造作もなかった。拍子抜けだったよ。この程度で盗賊団気取ってたのかってね。
リンウェになにも教えてやれなかったのは残念だ。なにせあいつ、隣の部屋で手下が殺されて、自分一人になったってまだ気付いてもいなかったんだ。
最後は、あいつがいる部屋のドアにそこのテーブルにあったフォークを投げつけて、物音に顔を出したところを、サッとな。
その程度のくせにご大層に旗印まで作って掲げていたのが馬鹿らしくてさ。思いつきで燃やしてやったんだが、あれはちょっとやりすぎだったかもな。そもそも建物の中で燃やしたら、煙の行き場がなくて俺一人が煙くて大変だったっていうさ。
そんな馬鹿やらなきゃ100点だったかもしれないが、ま、おかげで90点ってところか。
だがまあ、他の場所に仲間がいたとすれば、いい見せしめにはなっただろう。とはいえ、それっきりサマーんちゃらなんて聞くこともなかったから、はっきりとは知らない。仲間なんていなかったのか、恐れをなして逃げたのか。
ともあれ、砦……ていうか洞窟から出ると、あたりはまだ暗かった。
TCとニラナイにはできるだけ早く報告してやったほうがいいだろうが、さすがに夜中じゃどうしようもない。
ウィンドヘルムに戻ってもまだ夜明け前だったから、俺はそのままホールに宿を取った。一日に二度も来れば少しは興味を持たれるもんで、女主人の……なんて名前だったっけな。まあ、それほど話したこともなかったから、覚えてないな。とにかく彼女に少し勘繰られた。ニラナイとなに話してたのかとか。そのあたりは年増の習性みたいなもんか。
だから俺は、彼女からちょっといい話を聞いて探検に行ったんだ、なんて当たり障りのない嘘をついておいた。実際の戦果はほぼ完璧だったが、女将にはまあまあって言っておいて、部屋を用意してもらった。アルゴニアンだから外で寝ろなんて言わないで、当たり前に泊めてくれるだけでも、ノルド至上主義の街じゃありがたいよ。
それで翌日、俺はまず市場に向かうニラナイを呼び止めて、もう心配ないってことを伝えた。
彼女は何度か念を押してから、本当にほっとした様子になった。それで、「いつでも、"なんでも"持ってきてね」ってね。ギルドにも連絡しなきゃいけないし、忙しくなるって、楽しそうだった。
それから当然、TCのところだ。少しでも早いほうがいいだろうと、俺は農園に向かった。彼は丁度畑に出るところで、俺がロケットを差し出すと、もう言葉もない様子でさ。しばらくじっと見つめてた。そして、あいつらはどうなったって言うから、もう誰も二度と口をきくことはないってだけ言っておいた。さすがに、素人さん相手に「皆殺しにしてきた」は過激すぎるもんな。
TCは、ギルドがウィンドヘルムで活動するなら、また以前のように支援すると、真剣な顔で約束してくれた。
ブッチャーの件はノータッチだった。それはまあ、TCだって別の奴が調べてくれてるってことを知ってただろうしな。たぶん……殺されるだけなら災難、切り刻まれるのは悲惨だとまだ諦めがついても、もしかしたらって話だが、もう一つの"許せないこと"のほうが、問題だったんだろ。
こうして俺は、前座仕事ってわりにはヘビーな一件を終わらせた。
ウィンドヘルムには有力な後見人ができたし、ニラナイっていういい故買屋も取り戻せた。ギルドに持ち帰る報せとしては最高だろう。
一晩休んで、報告も済ませて、その日は雪も降ってなくて―――俺はそろそろ、覚悟を決めた。
→第七章へ
|  ウィンドヘルムとウインターホールドの間くらいにある、雪深い山奥の墓場だ。はっきり言って、他にはなにもない。ただ雪。岩肌が少し見えるかどうか。そんな場所に、穴を掘って周囲を石組みで覆っただけの入り口があった。
ウィンドヘルムとウインターホールドの間くらいにある、雪深い山奥の墓場だ。はっきり言って、他にはなにもない。ただ雪。岩肌が少し見えるかどうか。そんな場所に、穴を掘って周囲を石組みで覆っただけの入り口があった。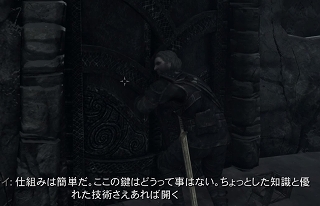 さあ、いよいよ侵入だ。
さあ、いよいよ侵入だ。 メルセルと、女だった。
メルセルと、女だった。 ただしそれは、カーリアにも俺にもまったく見たこともないような文字で書かれていた。
ただしそれは、カーリアにも俺にもまったく見たこともないような文字で書かれていた。 種族が違うとなかなか顔が覚えられないものだが、彼女はそろそろ俺を見分けられるようになっていていた。
種族が違うとなかなか顔が覚えられないものだが、彼女はそろそろ俺を見分けられるようになっていていた。 中に入ると、洞窟はすぐに、人工の建物につながっていた。奥に牢屋があったところを見ると、元は小さな砦だったんだろうな。だがそこにいた連中は、全部で15人に満たなかったのは確かだ。
中に入ると、洞窟はすぐに、人工の建物につながっていた。奥に牢屋があったところを見ると、元は小さな砦だったんだろうな。だがそこにいた連中は、全部で15人に満たなかったのは確かだ。 もちろん、造作もなかった。拍子抜けだったよ。この程度で盗賊団気取ってたのかってね。
もちろん、造作もなかった。拍子抜けだったよ。この程度で盗賊団気取ってたのかってね。